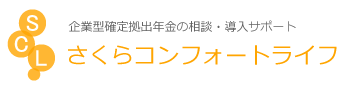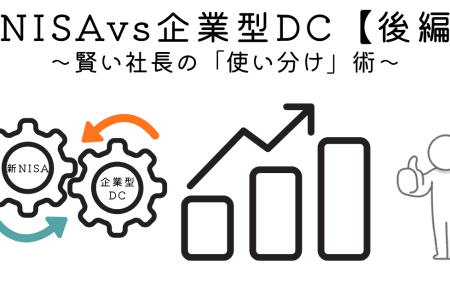退職金制度の導入相談で、「中退共と企業型DC、どちらがいいでしょうか?」というご質問をよくいただきます。
どちらも国の制度で安心感はありますが、私たちが企業型DCをおすすめするのには理由があります。実際に導入支援をしてきた中で見えてきた、両制度の決定的な違いをお伝えします。
まず知っておきたい基本的な違い
| 比較ポイント | 企業型DC | 中退共 |
| 役員の加入 | ○可能 | ×原則不可 |
| 掛金の調整 | ○柔軟に対応可 | △減額は困難 |
| 運用の主体 | 従業員が運用 | 機構におまかせ |
| 早期退職時 | 資産の持ち運び可 | 1年未満は掛け捨て |
| 採用への効果 | 高い差別化要因 | 最低限の安心感 |
1. 経営者自身の退職金準備ができるかどうか
企業型DCの場合 社長や役員も加入でき、掛金は全額損金処理が可能。しかも個人の社会保険料負担も増えません。
中退共の場合 役員は加入対象外。経営者の退職金は別途準備が必要です。
導入をご検討いただく企業様の多くが、「経営者の退職金も効率的に準備したい」とおっしゃいます。特に小規模企業では、この点が決め手になることが多いですね。
2. 経営環境の変化への対応力
企業型DCの場合 業績悪化時の掛金調整や、選択制DCによる従業員の拠出調整が可能。
中退共の場合 掛金月額の減額は、被共済者が同意したとき、または現在の掛金月額を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたときのほかはできません。
実際にサポートした企業様からは、「景気変動に対応できる柔軟性が安心につながる」という声をよくいただきます。コロナ禍でも、企業型DCを導入していた企業様の方が制度を継続しやすかったのが印象的でした。
3. 人材採用・定着への効果
これは導入後に実感される企業様が本当に多いポイントです。
企業型DCの場合 「投資教育付きの資産形成支援」として、特に若手人材へのアピール力が高い。
中退共の場合 「退職金制度あり」という安心感は提供できるものの、差別化要因としては弱い。
転職サイトでも「企業型DC導入」を前面に出す企業が増えており、採用競争力の観点から導入を決める企業様も多いです。
4. 従業員の将来への備え
企業型DCの場合
- 転職時に資産を持ち運べるポータビリティ
- 投資教育を通じた金融リテラシー向上
- 自分の判断で資産を育てる経験
中退共の場合
- 短期退職時の掛け捨てリスク(1年未満)
- 運用に関与できず、学びの機会が限定的
人材流動性が高まる中で、「どこに転職しても資産を持ち運べる」という安心感は、従業員の皆様にとって大きなメリットになっています。
5. 実際の導入企業様の声
「最初は投資教育が大変かと思ったけど、従業員が積極的に学ぶ姿勢を見せてくれて、会社全体の成長マインドが向上した」(製造業・従業員30名)
「役員の退職金も一緒に準備できるのが決め手でした。しかも採用でも『福利厚生が充実している会社』として評価してもらえるように」(サービス業・従業員15名)
なぜ企業型DCなのか?私たちの考え
中退共も優れた制度ですが、私たちが企業型DCをおすすめするのは、単なる「退職金制度」を超えた価値があるからです。
- 経営者の退職金準備
- 経営環境変化への対応力
- 採用競争力の向上
- 従業員の金融リテラシー向上
- 人材流動性への対応
これらすべてを同時に実現できる制度は、企業型DC以外にありません。
導入をご検討の企業様へ
もちろん、企業型DCにも投資教育の手間や制度理解の必要性など、乗り越えるべき課題はあります。
しかし、私たちはこれまで多くの企業様の導入をサポートしてきた経験から、これらの課題は適切な支援があれば十分に解決可能だと確信しています。
「うちの会社でも導入できるのか?」「従業員に理解してもらえるのか?」といった不安をお持ちの方も、まずはお気軽にご相談ください。
御社の状況に合わせた最適な制度設計から、従業員様への説明、導入後のフォローまで、全力でサポートいたします。