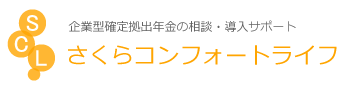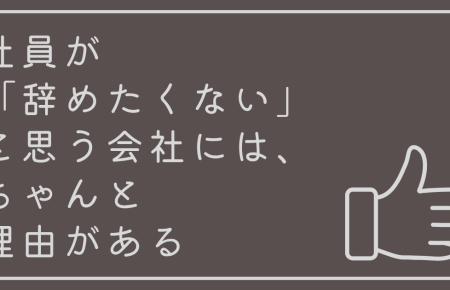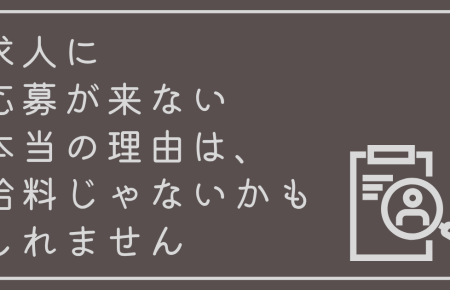【はじめに】
「従業員のために、より良い退職金制度を整えたい」
そんな想いから企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入を任された人事・総務のご担当者様。
でも、いざ調べ始めると―
どの金融機関を選べばいいのか迷ってしまう。何を基準に選定すべきなのか、資料を見ても専門用語が並び、正直よくわからない…。
「手数料が安いところに決めてしまって、後悔することは避けたい」
そんな不安を抱えている方が多いのではないでしょうか。
この記事では、実際にあった“よくある失敗事例”を通じて、企業型DC導入の際に本当に見るべきポイントと、長く信頼できるパートナーの選び方についてお伝えします。
【ケーススタディ】企業型DC導入でよくある3つの失敗
失敗1:手数料の安さに飛びついたら、サポートが全部オプションで割高に…
A社の人事担当者は、複数の金融機関から見積もりを取り、運営管理手数料が最も安かったB銀行に決めました。初期コストが低く、経営陣にも説明しやすいと判断したからです。
ところが導入後、新入社員の手続き、従業員からの問い合わせ対応、年1回の投資教育セミナーなど、必要なサポートがすべて「別料金」。結果的に、当初“高い”と思っていた他社よりも年間コストが上回ってしまいました。
《教訓》
「手数料が安い=トータルで安い」ではありません。
制度の運用にはさまざまなサポートが必要です。それらが基本プランに含まれているのか、オプション扱いなのかを必ず確認しましょう。安さに惹かれて選んだ結果、かえって担当者の負担やコストが膨らむ…そんなケースは珍しくありません。
失敗2:知名度で選んだら、従業員が選べる商品が限定的だった…
「大手なら安心だろう」
そう考えて、D社は長年付き合いのあるC信託銀行に導入を依頼しました。
ところが、制度説明会で若手社員から質問が飛び出します。
「なぜ、手数料の安い人気のインデックスファンドが無いんですか?」
調べてみると、C信託銀行のラインナップは、グループ会社が運用する手数料高めの商品ばかり。せっかくの制度も、従業員が選びたい商品を選べない仕組みでは、福利厚生としての意味が半減してしまいました。
《教訓》
知名度の高さや取引実績は安心材料のひとつかもしれませんが、それだけで判断するのは危険です。
従業員が将来に向けて主体的に資産形成に取り組むためには、質の高い運用商品が揃っていることが重要。低コストなインデックスファンドや多様なアクティブファンドなど、選択肢の幅があるかをしっかり確認しましょう。
失敗3:「導入だけ支援」の会社に頼んで、法改正時に孤立…
E社は導入コンサルティング会社に依頼し、スムーズに企業型DCをスタートできました。
しかし2年後、制度に関わる法改正があった際、社内での規約変更や従業員への対応について、どう動けばいいのか分からず、担当者は孤立してしまいます。
運営管理機関に問い合わせても、返ってくるのは事務的な返答だけ。
「この制度をなぜ導入したのか、その背景を理解して寄り添ってくれるパートナーがいれば…」と、強く感じたと言います。
《教訓》
企業型DCは導入して終わりではなく、そこからが本番です。
法改正、ライフステージの変化、継続的な投資教育など、長期的な視点で支えてくれるパートナーの存在が、制度運営の成功を左右します。最初から「伴走力」まで見て選ぶことが何より大切です。
【まとめ】選ぶべきは、「3つのバランス」と「伴走してくれるパートナー」
ここまでの失敗事例から分かるのは、運営管理機関を選ぶ際には、次の3つをバランスよく見極めることが不可欠だということです。
| コスト(手数料) | 初期費用だけでなく、トータルコストで考える |
| 商品(ラインナップ) | 従業員が納得して選べるよう、質・選択肢の幅ともに充実しているか |
| サポート(伴走力) | 制度を理解し、導入後も頼れる存在かどうか |
この3つがバランスよく揃っていて、なおかつ会社の風土や従業員のことまで考えて動いてくれる。そんなパートナーと出会えれば、企業型DCは確実に、貴社の強い武器になるはずです。
【おわりに】
「どこが自社にとって、本当に頼れるパートナーなのか?」
そんなお悩みをお持ちでしたら、どうぞ私たちにご相談ください。
特定の金融機関に偏らず、中立的な立場から、貴社にとって最適な選択を一緒に考えさせていただきます。